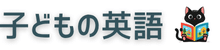ソースと聞いて、何を思い浮かべますか?
おそらく、多くの人が最初に思い浮かべるのは「とんかつにかけるアレ」じゃないでしょうか。
はい、料理に使う「ソース」ですよね。
でも、ニュースとかSNSの世界では「そのソースどこ?」とか「ソース付きでお願いします」なんて言い回しもよく見かけます。
この場合は「情報の出どころ」って意味で使われてます。
同じ言葉なのに、ぜんぜん違う意味に感じますよね。
しかも、なんか無関係っぽい。
でも実は、この2つの「ソース」には意外なつながりがあるんです。
ソースの語源は「源(みなもと)」
ちょっとまじめに説明しますと、「ソース(source)」という英単語の元々の意味は「源」や「起点」です。
つまり「どこから始まったか?」というニュアンスが含まれているんですね。
たとえば、川の始まりの場所を「水源(water source)」といったりします。
これと同じように、情報の出どころ、つまり「情報の水源」的な意味で「情報のソース」という表現が使われています。

で、ここからがちょっとおもしろい話なのですが……
料理のソースも「源」から来てる?
料理に使う「ソース」も、実は同じ語源から来ています。
フランス語の「sauce(ソース)」は、「salsa(サルサ)」というラテン語から来ていて、この「salsa」もまた「塩味の効いたもの」みたいな意味だったんですね。
そしてさらに遡ると、「sal(塩)」に行きつくんですが、これが「味の根源」としての意味合いを持っていたんです。
要するに、「ソース」は料理の味の決め手=料理の『味の源』としての立ち位置だった、ということです。
情報のソースが「話の根っこ」なら、料理のソースは「味の根っこ」だったわけですね。

言葉の意味って、思ったより柔軟
こうやって考えてみると、「ソース」という言葉が、
・情報の源としての「ソース」
・料理の味の源としての「ソース」
というように、「〇〇の根っこ」という意味で共通しているのがわかってきます。
つまり、「どこから来たか?」という感覚がベースにあるんですね。
普段、意味がまったく違うように感じていた言葉でも、こうして語源をたどると「なるほど!」ってなることが多いです。
とはいえ、意味のズレはやっぱりある
とはいえ、「ソース付きで発言して」と言われて、「ウスターソースを添えるのか?」とは誰も思わないので、日常的な使われ方としてはかなりズレてます。
だから、混乱するのも無理はないです。
でも、このズレこそが言葉の面白さでもあるな〜と思うんですよね。
というわけで
「ソース」という言葉を深掘りしてみると、思っていたより奥深くて、料理と情報の両方に通じる「源」という共通点が見えてきました。
普段何気なく使っている言葉でも、ちょっと立ち止まって意味を考えてみると、新しい視点が得られたりします。
ぜひ、身の回りの「なんでこの言葉こう使うんだろう?」っていう言葉を、たまに調べてみると楽しいかもしれません。
ソースだけに、味わい深い話でしたね!
ではでは〜。