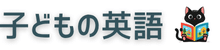こんにちは!
普段、何気なく使っている言葉の中に、ふと「あれ?」と立ち止まってしまうような不思議な発見が隠されていること、ありますよね。
先日、スマートフォンの画面に「バッテリー残量低下」の表示が出て、慌てて充電器を探しました。そしてその夜、テレビの野球中継では、解説者の方が「今日の試合は、あの最強バッテリーが鍵を握っていますね」と熱く語っていました。
「バッテリー切れ」のバッテリーと、「最強バッテリー」のバッテリー。
かたや電気をためる「電池」のことで、かたや野球の「ピッチャーとキャッチャー」という人のコンビのこと。
指しているものは全然違うのに、なぜか全く同じ「バッテリー」という言葉が使われています。
これって、考えてみるととても面白いことだと思いませんか。今日はこの、言葉の不思議なつながりについて、一緒に探ってみたいと思います。
「偶然同じ音」では片付けられない、深いワケ
「まあ、日本語に訳したら、たまたま同じ音になっただけでしょ?」
きっと、多くの方がそう思われるかもしれませんね。僕も以前はずっとそう考えていました。
でも、実はこの二つの「バッテリー」、偶然の一致なんかではないんです。
驚くことに、どちらも英語のbatteryという、たった一つの言葉がルーツになっています。
この事実を知った時、「じゃあ、その『バッテリー』の本当の最初の意味って、一体何だったんだろう?」と、新たな疑問が頭に浮かんできますよね。
そのモヤモヤした気持ち、なんだか放っておけない感じがします。
というわけで、ここからは「バッテリー」という言葉の語源をたどる、ちょっとした時間の旅にご案内します。
すべての始まりは「打つ」という言葉だった
batteryという言葉。その一番最初のルーツをさかのぼっていくと、ラテン語の「打つ・叩く」という意味の言葉にたどり着きます。
これをものすごくざっくりいうと、何かを繰り返しコンコンと叩いたり、力強く打ち付けたりする、そんなイメージです。
実は、野球の「バット(bat)」や、戦いを意味する「バトル(battle)」も、みんなこの言葉から生まれた親戚のような単語なんです。
こう考えると、少しだけbatteryの持つ本来の力強い雰囲気が、感じられるような気がしませんか。
「打つ」が「砲台」になり、そして「電池」へ
さて、この「打つ」という言葉は、やがて軍事の世界で使われるようになります。
昔の戦争で、お城の分厚い壁を大砲で何度も「打つ」ことから、「砲撃する」という意味で使われ始めました。
そして、そこからさらに意味が発展して、「大砲がずらりと並べられた場所」、つまり「砲台」そのものをbatteryと呼ぶようになったのです。
この「砲台」こそが、全ての「バッテリー」の物語の出発点でした。
では、なぜこの物々しい軍事用語が、私たちの生活に欠かせない「電池」の意味になったのでしょうか。
それは18世紀のこと。かの有名な科学者ベンジャミン・フランクリンが、電気をためる装置(ライデン瓶という、初期の蓄電器です)を、ずらっと横に並べて実験を行っていました。
その様子が、まるで大砲がいくつも並んだ「砲台」にそっくりに見えたそうです。
このユニークな発想から、フランクリンはその装置一式を「バッテリー」と名付けました。
これが、「電池」としてのバッテリーの語源になったと言われています。面白いですよね。
野球のバッテリーも、やっぱり「砲撃」がルーツ
ここまでくれば、野球の「バッテリー」の謎も、もうお分かりかもしれませんね。
はい、ご想像の通りです。
野球のバッテリーの語源も、やはりこの「砲台」から来ています。
話は1860年代、アメリカが南北戦争で揺れていた頃にさかのぼります。
当時、「野球の父」とも呼ばれたヘンリー・チャドウィックという、とても有名なスポーツ記者がいました。
彼は、チームの強力な投手陣が次々と速球を投げ込む様子を、まるで軍隊の「砲台」が火を噴くようだ、とその攻撃力になぞらえてbatteryと表現したのです。
最初はピッチャー陣全体を指す言葉だったんですね。
それがいつしか、その力強い球を一身に受け止めるキャッチャーも一つのユニットと見なされるようになり、今の「ピッチャーとキャッチャーの二人組」を指す言葉として、私たちに馴染み深いものになっていったのです。
最後に:言葉の裏側に広がる世界
というわけで、「バッテリー切れ」も「最強バッテリー」も、その語源をたどれば「打つ」→「砲台」という、同じ一つのルーツに行き着く、というお話でした。
普段、当たり前のように使っている言葉の裏側をそっと覗いてみると、そこには壮大な歴史や、昔の人のユーモラスな発想が隠されています。
言葉の不思議なつながりを知ると、いつもの毎日が、ほんの少しだけ豊かに感じられるかもしれませんね。