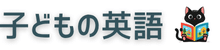こんにちは!
毎日当たり前のように使っている言葉が、ある日突然、まったく新しい顔を見せてくれることってありますよね。
ニュースを見ていると、「次の大臣のポストには誰が…」なんて言葉を耳にします。
そして街角では、手紙を出すために赤い郵便「ポスト」を探し、家に帰ればスマートフォンで「今日の出来事をポストしようかな」と考えたりします。
「地位」や「役職」のこと。
手紙を入れる「箱」のこと。
SNSに文章を「投稿する」という行為のこと。
これだけ違うものを指しているのに、全部同じ「ポスト」という言葉が使われています。
これって、冷静に考えると、本当に不思議な感じがしませんか。今日はこの、日常にそっと隠れている言葉の謎を、一緒に楽しく解き明かしてみたいと思います。
「偶然でしょ?」では片付けられない、一つのルーツ
「きっと、それぞれ違う言葉が、日本語にしたらたまたま同じ音になっただけでしょ?」
はい、そう考えるのが自然ですよね。これだけ意味が違えば、そう思ってしまうのも無理はありません。
でも実は、この三者三様の「ポスト」、偶然の一致なんかではなかったんです。
驚くことに、これらすべて、英語のpostという、たった一つの言葉がルーツになっています。
この事実を知ると、今度は「じゃあ、その言葉の一番最初の意味って、一体何だったんだろう?」って、新たな好奇心がむくむくと湧いてきますよね。
そうなると、ますます気になってきますよね。
というわけで、ここからはpostという言葉がたどってきた、面白い道のりにお付き合いください。
すべての始まりは、地面に立つ一本の「柱」
postという言葉。その一番最初の語源をさかのぼっていくと、ラテン語のpostisという言葉にたどり着きます。
もともとは、地面にドーンと立てられた「柱」や「杭」という、とてもシンプルな意味でした。

お家の柱、柵の杭、あるいはサッカーの「ゴールポスト」も、この仲間ですね。これが、postという言葉の、最も基本的で古いイメージなんです。
でも、一本の「柱」が、どうやって役職や手紙、SNSの世界につながっていくのでしょうか。
ここから、この言葉は大きく3つの物語へと分かれていくのです。
物語1:「持ち場」としてのポスト(役職・地位)
まず、ニュースで聞く「大臣のポスト」です。
昔、兵士が見張りをする場所には、目印として「柱(post)」が立てられていました。
そこから、postは兵士が立つべき「持ち場」や「部署」を意味するようになったのです。

「君のポスト(持ち場)は、あの見張り台だ」といった感じですね。
この「持ち場」という意味が、やがて軍隊だけでなく、政府や会社など、さまざまな組織における「役職」や「地位」を指す言葉へと発展していきました。
一本の柱が、人の立つべき場所を示すようになったんですね。面白い変化です。
物語2:「情報伝達」のポスト(郵便)
次に、おなじみの「郵便ポスト」です。
まだ新聞もなかった時代、ヨーロッパの街では、広場に立つ「柱(post)」が、今でいう掲示板の役割を果たしていました。人々は、そこに大切な知らせを貼り出して情報を共有していたのです。
この「柱にお知らせを貼り出す」という行為から、postは「情報を公にする」という意味を持つようになりました。
そして、その知らせを次の街へ、また次の街へと馬で運ぶ「中継所」のこともpostと呼ぶようになります。この中継所のネットワークが、やがて国全体の「郵便制度(the post)」へと発展しました。
私たちが手紙を入れる箱は、この郵便制度(post system)の一部だから、「郵便ポスト」なんですね。
物語3:「投稿」としてのポスト(SNS)
最後は、SNSへの「ポスト」です。これはもう、お分かりかもしれませんね。
街の「柱」にお知らせを貼り付けて「情報を公にする」という意味が、そのまま現代に受け継がれたのが、この用法です。
インターネット上の電子掲示板やSNSは、いわば「現代の、デジタルの柱(広場)」。
そこに自分の考えや写真を「掲示する」行為だから、「ポストする」と言うのです。
なんだか、SNSに投稿する時、昔のヨーロッパの広場に立っているような気分になりませんか。
最後に:言葉の裏側に広がる世界
というわけで、「役職」も「郵便」も「SNSへの投稿」も、その語源をたどれば、すべて地面に立つ一本の「柱」に行き着く、というお話でした。
ちなみに、「ポスト平成」のように「〜の後」を意味するpost-は、ラテン語で「後」を意味する別の言葉が語源の「そっくりさん」です。言葉の世界は奥深いですね。
普段、当たり前のように使っている言葉の裏側を覗いてみると、そこには人々の暮らしの知恵や、壮大な歴史が隠されています。
いつもの言葉が、今日からほんの少しだけ、違って見えてくるかもしれませんね。